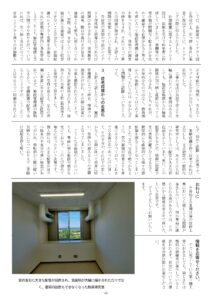皆さまのご協力をいただき、本日、新潟大学学長に下記のように文書を送付いたしました。数多くのお声をお届けいただき、心より感謝申し上げます。
新潟大学職員組合中央執行委員会
=========
新潟大学学長 牛木辰男殿
2025 年8月29日
新潟大学の発展のためにご尽力のことと拝察いたします。
文部科学省は「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」を見直し、その支援対象を日本人限定とし留学生を除外することを決めました。この施策について、新潟大学職員組合として強い懸念を表明いたします。
生活費支援を日本人学生に限定するこの方針は、明白な国籍差別であり、地方国立大学である本学の教育研究環境に深刻な影響をもたらします。18歳人口減少の中、優秀な留学生は本学の博士課程維持に不可欠な存在です。今回の政策転換により、博士課程の定員充足がさらに困難となり、研究科の縮小や閉鎖の危険性も懸念されます。
学問に国境はありません。優秀な研究者を国籍で選別することは、本学が築いてきた国際的な教育研究環境を破壊し、地域の知的拠点としての役割を根本から脅かすものです。
上記の趣旨で署名を募りましたところ、本学教職員・学生・市民より以下のように87名より賛同の署名をいただきました。
記 博士課程学生支援制度の国籍差別的見直しに対する要望
新潟大学長におかれましては、国立大学協会等を通じて政府に対し、博士課程学生支援制度における国籍による差別的取扱いの撤回と、国籍を問わない公正な支援制度の維持を強く働きかけていただくよう要望いたします。
新潟大学職員組合 中央執行委員長 逸見龍生
計87筆
以上
署名附帯意見
・本要望書に全面的に賛同します。今回の政府方針は、本学が築き上げてきた国際的な信頼と多様性を根底から覆す暴挙です。すでに留学生だけでなく、多くの日本人学生や教職員の間にも動揺が広がっています。このような時だからこそ、牛木学長のリーダーシップを求めます。政府への働きかけとともに、私たち新潟大学の全学生・教職員に対し、大学としてこの事態にどう向き合うのか、その毅然とした姿勢をメッセージとして示していただきたく、強く要望いたします。 不安の渦中にある私たちにとって、学長の言葉が道標となります。
・このような動きは、日本に暮らす人々にとっても、学術にとっても何も豊かさをもたらさないばかりか、「外国人」という仮想敵を仕立てて一時的な不満の矛先とし、根本的な問題から目をそらす、極めて愚かで子どもじみたふるまいだと思います。この方針を貫くならば、世界中から日本は極めて差別的であり、またそれを支持するような国民であると評価されることになるでしょう。それはどれほど大きな損失でしょうか。
・国籍を問わずに学べるようにしていただきたいです。差別を助長する真似はお止めください。
・我が国のアカデミアが広く世界に開かれたものであることを強く望みます。
・留学生数が相対的に多く見えるには、学位取得しても就職が困難な日本の状況から、国内大学出身者が院進したがらないため。まず企業や行政が学位取得者の価値を認めて採用するのが先です。
・20世紀にアメリカが大国になったのは、奨学金と支援で世界中の優秀な頭脳を集め、ポストも用意して彼らの一定数をアメリカにとどめたおかげ。
・今、海外の優秀な学生を日本に呼ばなければ、ほかの国に取られるだけです。
・すでに留学生がいなければ研究が回らず、水準も維持できなくなっており、割を食うのは日本の院生・学生です。また、「日本人・留学生」という分け方に定住外国人についての視点がないこともおかしいです。
・博士課程の学生は、すでに「学生」という枠を超え、「研究者」としての役割を担っています。にもかかわらず、安心して研究に取り組むための支援策から外国籍留学生を排除することは、日本が人材を軽視しているかを示すものです。このような排外的な制度の下
で、日本が世界中の優秀な研究者を本当に惹きつけ、育成し、守ることができるのか――その姿勢自体が厳しく問われるべきです。
・実際来日している留学生の方、とくに院生は優秀な方が多く、日本人を支援せよという国民感情に流されてしまっているだけに感じる。その出生により支援を制限するということは研究の発展という視点から言えば健全であるとは言えない。
・学問に人種、民族、国籍による差別があってはなりません。治療もそうではありませんか。
・優秀な研究者のために、そんな行為は反対したいと思います。よろしくお願い致します。
・ポピュリズムに迎合した、信じられない愚策である。人類が築いてきた科学の礎が今まさに崩されようとしている。改正を強く望む。
・修了した後の生活の算段が取れるよう、非常勤でない安定した研究職雇用枠も増えるといいと思います。特に文系。
・労働組合から提起されたこのような運動に敬意を表します。
・呼びかけ文に賛同します。学生支援制度の差別的運用に反対します。
・私は現在、新潟大学に所属しており、来年度には新潟大学院への進学を予定しています。大学時代に出会った優秀な学生たちが国籍に関係なく大学院で快適に学べるよう、当署名に賛同します。
・短絡的な排外主義に流されないでほしいです。国籍で一定の人を排除することが結果的には自分たちの首をしめることになります。
・いち早く見直しの声を上げる、新潟大学の職員組合に敬意を表し、連帯します。共に頑張ります。
・アジアなどの外国人留学生その他が多い新潟大学からぜひ働きかけおねがいします
・国籍による差別的な取り扱いに強く反対します。優秀な研究者の支援に国籍は関係なく、学問の自由と多様性を守るべきだと考えます。公平で開かれた博士課程支援制度の維持を強く希望します。
・大阪大学在学の学部生です。日本人の税金だから外国人に使うな、という安易な意見に反対します。研究機関はグローバルに開かれた施設であるべきであり、そのためには相互の国が留学生を支援する制度があって然るべきです。是非提言をお願いします。
・国際的な研究教育環境の維持を是非お願いします。
・日本人、外国人にかかわらず学びたい人への教育保障はなされるべきです。外国人留学生は熱心で優秀、むしろ日本の学生がかれらから学ぶべきことが多くあり良い刺激をいただいています。
・人を見捨てる社会はいつか自分も捨てられる社会となってしまいます。そんな寂しい社会にならないよう外国人留学生支援の継続を強く望みます。”
・今回の支援制度見直しに関しまして、一つ強く疑問に思っている点がございます。私の両親は日本で働き、長年にわたって日本社会の一員として納税も行っております。税金を徴収する際には、国籍に関係なく外国人にも義務が課されている一方で、いざその税金をもとにした支援を分配する段階になると、外国人が対象から外されるというのは、どうしても納得がいきません。
・私は永住者で、日本人と同じように所得税、社会保険料を支払っています。一部のインターネットのコメントでは留学生は税金を支払っていなく、日本の資源を享受しているのみで、除外すべきとのコメントがありますが、私は来年より日本の税法の研究し、日本の法制度に貢献するために、博士号を取得することを考えています。日本人と同じように税金を納め、日本国のために研究を行いますが、国籍のみで制度から除外することは断固反対します
・昨今の日本人にのみという考え方の風潮全般をとても残念に感じています。時間の必要な教育や研究への国のこのような政策転換が現場にかける直接的な混乱と不利益を思うと胸が痛いです。
・「太平洋戦争」後に設立されたフルブライト奨学金制度が、「奨学生に対してそれぞれの専門分野の研究を進めるための財政的援助を行うとともに、何らかの形で日米の相互理解に貢献できるリーダの養成を目的」として、利根川進氏や小柴昌俊氏のようなノーベル賞受賞者、日本が国際連合に加盟して初の国連職員となった明石康氏など、錚々たる人材を輩出してきたことは周知の事実です。「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」には、そのような「相互理解」に関する理念が存在しないのでしょうか。同プログラムの「事業概要」には「生活費相当額及び研究費の支給や、キャリア開発・育成コンテンツ(国際性の涵養、学際性の涵養、キャリア開発、トランスファラブルスキルの習得、インターンシップ等)をはじめとする様々な支援」が謳われています。学問・研
究の発展に国籍要件は必要ありません。日本国籍でない学生に「生活費を支給しない」という文部科学省の国籍差別的な施策は、留学生の日本に対する「理解」に大きなマイナスをもたらすことでしょう。
・新潟大学には世界55の国・地域から約480名の留学生が在籍しています。それ以外に、日本で生まれ育った、日本国籍ではない学生もいます。日本外務省のH.P.には「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第2回報告(仮訳文)」として、以下のように記されています。
(4) 教育の権利の実現のための援助
経済発展を目指す開発途上国にとって不可欠なのは、人的資源の育成である。しかるに、開発途上国においては、一般に社会サービス部門の整備が遅れ、とりわけ教育サービス提供の立ち遅れが顕著である。我が国では、このような教育サービスの立ち後れが、経済開発の不可欠の要素たる人的資源の育成を阻害するものであることに鑑み、ソフト・ハード両面にわたり様々な援助を実施している。
我が国は、開発途上国の人的資源の育成に資するべく我が国高等教育機関への留学生の受入れを積極的に推進している。我が国は、「国費留学制度」をはじめとする各種施策を総合的に推進しており、良質の高等教育サービスを広く世界に提供すべく努めている。
「我が国は、開発途上国の人的資源の育成に資するべく我が国高等教育機関への留学生の受入れを積極的に推進している。我が国は、「国費留学制度」をはじめとする各種施策を総合的に推進しており、良質の高等教育サービスを広く世界に提供すべく努めている。」との言葉どおり、開発途上国の留学生に限らず、日本国内の外国籍学生が安心して研究生活を送れるよう、国立大学法人新潟大学として、今回の文部科学省の方針に反対してくださることを要望いたします。
参照URL
https://www.jst.go.jp/jisedai/spring/outline/index.html (JST 科学技術振興機構)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b1_004.html (外務省)
・本学は,将来ビジョン2030において,「世界に開かれた「知のゲートウエイ」の役割を明確にする」と宣言しています。この宣言と国籍による差別とは相容れないと考えます。積極的な行動をおねがいします。
・大学で博士課程に進む外国人として、今回の「SPRING支援制度における国籍制限」の方針には、深い遺憾の意を表します。私たち留学生は、日本の研究・産業、そして地域社会に貢献する意志を持って来日し、言語や文化、生活上の困難を乗り越えながら、日々真摯に学術活動に取り組んでいます。そのような中で、国籍を理由に支援の対象から排除するという政策は、研究の国際化や多様性の尊重という、これまで先輩方が積み重ねてきた価値観に明らかに逆行するものです。今回のSPRING制度の見直しは、単なる「支援の限定」ではなく、「排除の始まり」と受け止めざるを得ません。次は、留学ビザの制限や奨学金の打ち切りが待っているのでしょうか。
・「日本にトランプはいない」「学問の扉は、誰に対しても公平に開かれている」――そう胸を張って言える社会であってほしいと願います。だからこそ、私は今回の制度見直しに強く反対します。
・国籍差別はやめて欲しいと考えております。
・博士課程学生支援制度の国籍差別的見直しに断固反対します
・国籍を問わない公正な支援制度の維持こそが、アカデミアの競争力の源であると考えます。
・日本は資源がなく、人材、頭脳で勝負するしかありません。外国人の学生が東大の先生になるかもしれません。人材確保、流出防止は重要です。すでに国外に日本の頭脳が流出しているのに(給与が低いから)文科省は危機感がないのでしょうか。
・外国人差別を許してはいけません。要望文の趣旨に賛同します。